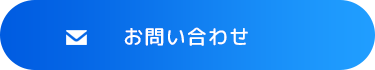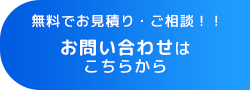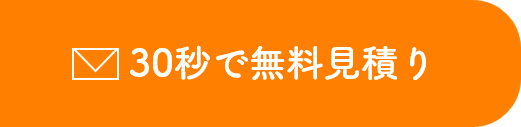生活保護を受けていた方の遺品整理をスムーズに進めるコツ2025.01.30
生活保護を受給していた人が亡くなったとき、遺品整理をどう進めれば良いか、戸惑ってしまうケースは少なくありません。
相続人がいる場合は親族が対応しますが、相続放棄されることもあり、誰が遺品整理をするのか曖昧になることもあります。
賃貸物件では大家や管理会社が関わることもあり、費用の負担が問題になることもあります。
本記事では、生活保護を受給していた人が亡くなった際の遺品整理について、費用負担の考え方や、自治体の支援制度の活用方法などを解説します。
Contents
生活保護受給者が亡くなったら、遺品整理は誰が行う?
生活保護を受給していた人が亡くなった場合、遺品整理は誰が行うのか明確に決まっているわけではありません。
相続人がいる場合は基本的に親族が対応しますが、相続を放棄すると整理を進める人がいなくなります。
賃貸物件では、部屋を管理する大家や管理会社が関わることもあります。
費用の負担や自治体の支援についても事前に確認しておくと、スムーズに対応しやすくなります。
遺品整理をするのは相続人?それとも大家?
生活保護を受給していた人が亡くなった場合、遺品整理を行うのは基本的に相続人です。
相続人とは、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹など、法律で財産を引き継ぐ権利がある人のことを指します。
遺品整理は相続の一部と考えられているため、まずは相続人が対応することになります。
しかし、相続人がいない場合や相続を放棄した場合、遺品整理を進める人がいなくなります。
相続人がいない場合、賃貸物件では大家が対応を求められることがあります。
部屋に遺品が残ったままだと、新しい入居者を迎えることができないため、遺品整理を進めなければなりません。
賃貸契約に連帯保証人がいたとしても、遺品整理の責任までは負わないのが原則です。ただし、契約内容によっては例外もあるため、事前に確認することが大切です。
相続人が見つからない場合は、自治体に相談できることもあるため、早めに問い合わせるとスムーズに進められます。
費用は誰が負担する?自己負担を避ける方法
遺品整理にかかる費用は、原則として相続人が負担します。遺品整理は相続の一環と考えられているため、相続を受ける人が整理の責任を持つことになります。
ただし、故人に財産がほとんどなく、相続人の経済的負担が大きい場合は、自治体に相談できるケースもあります。
生活保護を受けていた人が亡くなった場合、自治体が支援することもありますが、対応は地域によって異なります。
遺品整理の負担を減らすためには、まず自治体の福祉窓口に問い合わせて、利用できる制度があるか確認するとよいでしょう。
また、遺品整理業者を利用する場合は、料金が業者によって異なるため、複数の見積もりを取るのがおすすめです。
相続人がいない場合は、大家が遺品整理を行うことになりますが、費用は大家自身が負担するのが一般的です。
特に孤独死などで特殊清掃が必要になった場合は、費用が高額になることもあるため、事前に対応策を考えておくことが望ましいです。
費用を抑えて遺品整理を進めるには?
遺品整理の費用を抑えるには、身近な支援を活用しながら、無駄な支出を減らすことが大切です。
自治体の制度やリサイクルサービスを利用すれば、整理の負担を軽減できます。
業者を利用する際も、必要な作業だけを依頼することで、費用を抑えながら進めることが可能です。
費用を抑えて遺品整理を進めるには?
遺品整理の費用を抑えるには、自治体の支援を活用し、自分でできる作業を増やすのがポイントです。
生活保護を受けていた人が亡くなった場合、自治体が葬儀費用を補助する「葬祭扶助」などの制度を設けていることがあります。
自治体の福祉事務所への事前申請が必要なため、興味があれば問い合わせてみましょう。
自分たちで仕分けを行い、大きな家具や家電は自治体の粗大ごみ回収を活用すると、処分費用を節約できます。
自治体によっては、遺品処分に関する支援制度があるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
また、買取サービスを利用することで、整理費用の負担を軽減できます。
使える家電や家具をリサイクルショップに持ち込んだり、買取対応のある業者に依頼したりすると、費用を抑えられます。
遺品整理業者は本当に必要?
遺品整理は自分たちで進めることもできますが、遺品の量が多い場合や、作業する人が少ない場合は、業者に依頼することで負担を減らせます。
業者に頼むと、仕分け・搬出・処分まで一括で対応してもらえるため、短時間で整理を終えられます。遠方に住んでいる場合や、高齢で作業が難しい場合にも利用しやすい方法です。
ただし、業者を利用すると費用がかかるため、必要な作業だけを依頼してコストを抑えるのも一つの方法です。
事前に貴重品や必要なものを整理し、処分だけを業者に任せることで、無駄な費用を減らせます。
また、買取サービスを行っている業者なら、買い取った分の金額を整理費用から差し引いてもらえることもあります。
大切な遺品を丁寧に扱うためにも、どこまで自分たちでできるのかを考え、業者のサポートが必要かどうかを判断するとよいでしょう。
料金トラブルを防ぐための業者選びのコツ
遺品整理業者を選ぶときは、料金体系が明確で、信頼できる業者を選ぶことが大切です。
一方で、あまりにも安い料金を提示する業者には注意が必要です。
作業員の人数を減らしたり、不法投棄を行ったりするケースもあり、トラブルになる可能性があります。
事前に口コミや実績を確認し、適正な対応をしているかを見極めることが重要です。
また、契約内容をしっかり確認し、不要なオプションが含まれていないかチェックしましょう。
遺品整理や搬出のみを依頼し、処分は自治体の回収を利用するなど、工夫することで費用を抑えられます。
相続放棄すると遺品整理はどうなる?
相続放棄をすると、故人の財産や負債を一切引き継がなくなります。
ただし、遺品整理の責任が完全になくなるわけではありません。
賃貸物件の明け渡しや残された家財の処分について、誰が対応するのかを事前に確認するようにしましょう。
相続放棄の手続きをする前の注意点
相続放棄を考えている場合、手続きを始める前に注意したい点がいくつかあります。
まず、故人の遺品や財産を処分すると、相続を承認したとみなされることがあり、相続放棄ができなくなることもあります。
例えば、貴金属や骨董品を売ったり、預貯金を引き出したりすると、相続したと判断される可能性があります。
また、賃貸物件の解約や携帯電話の解約などの手続きも注意が必要です。相続人が解約手続きを行うと、相続を認めたと判断されることがあります。
そのために、慌てて手続きを進めずに、まずは相続放棄の手続きを完了させることが大切です。
相続放棄の手続きを進める前に、遺品や財産の状況をしっかり確認し、専門家に相談しながら慎重に進めましょう。
不明な点があれば、弁護士や司法書士にアドバイスをもらうことで、安心して手続きを進めることができます。
相続放棄後の遺品は誰が処理する?
相続放棄をした後、故人の遺品は基本的に相続財産管理人が処理を行います。
相続財産管理人とは、家庭裁判所が選任する人で、遺品の整理や財産の清算を担当します。
相続人全員が相続放棄をした場合、管理人が決まるまでは遺品がそのまま残るため、放置しないように注意が必要です。
また、故人が賃貸住宅に住んでいた場合、連帯保証人がいると、部屋の片付けや原状回復の対応を求められることがあります。
特に孤独死があった場合は、特殊清掃が必要になり、大家や管理会社が処理を進めることもありますが、費用は保証人や管理人が負担することが多いです。
相続放棄をしても、一時的に遺品を管理しなければならないこともあるため、事前に自治体や弁護士や司法書士に相談しておくと安心です。
大家が知っておくべき、遺品整理の対応策
賃貸物件の入居者が亡くなった場合、大家は遺品整理や契約解除の対応を進める必要があります。
相続人や保証人がいれば連絡を取り、相続人や保証人がいない場合は法的手続きが必要になることもあります。
賃貸物件で入居者が亡くなったら最初にやること
賃貸物件の入居者が亡くなった場合、まずは警察に連絡しましょう。
入居者と連絡が取れない、異臭がするなどの通報があった際は、勝手に部屋へ入らず、警察と相談しながら状況を確認します。
室内で亡くなっていた場合は、警察が現場を確認し、必要に応じて検視を行います。
その後、連帯保証人やご家族へ連絡し、賃貸契約の手続きや遺品整理について話し合います。
相続人がいない、または相続を放棄する可能性がある場合は、家庭裁判所を通じて相続財産管理人を選ぶ流れになることもあります。
また、原状回復のために特殊清掃が必要なケースもあります。臭いや汚れの程度によって作業が変わるため、専門業者に早めに相談することでスムーズに進められます。
費用負担や未払いの家賃については、契約内容を確認しながら慎重に話し合いを進めましょう。
連帯保証人がいないとき、大家はどう対応する?
入居者に連帯保証人がいない場合、大家がどのように対応するか考える必要があります。
まず、故人に相続人がいるかを確認し、役所や警察と連携しながら連絡を取ります。
もし相続人がいない、または相続放棄をした場合、家庭裁判所を通じて相続財産管理人を選任する手続きが必要になることもあります。
相続人も保証人もいない場合、遺品整理や原状回復の手続きは大家が進めることになります。
専門の遺品整理業者や特殊清掃業者に相談しながら、スムーズに片付けを進めるのがよいでしょう。
また、賃貸契約時に家財保険や孤独死対応の特約がついている場合は、補償内容を活用できるか確認してください。
今後のリスクを減らすためには、賃貸契約の際に保証会社を利用する、身元保証人を設定するなどの対策を考えておくと安心です。
単身の生活保護受給者が亡くなったら、家財はどうする?
単身の生活保護受給者が亡くなると、家財の整理や処分を誰が行うかが問題になります。
相続人がいる場合は遺族が対応しますが、相続放棄されることも少なくありません。
自治体の支援や処分方法を知っておくと、負担を減らすことができます。
費用をかけずに処分する方法とは
生活保護受給者が亡くなった後、家財の処分にかかる費用は基本的に遺族や関係者が負担します。
ただし、親族が相続を放棄した場合は、費用をかけずに処分する方法を検討する必要があります。
自治体の粗大ごみ回収を利用すると、比較的安価に処分できます。ただし、生活保護受給者の死後は手数料の免除制度が適用されない点に注意しましょう。
リサイクルショップや不用品回収業者を活用し、売却や無料回収が可能なものを見極めると、費用負担を減らせます。
自治体の制度やサポートを活用しよう
故人が生活保護を受給していた場合、自治体の制度を利用することで家財の処分費用を抑えられる可能性があります。
例えば、葬祭扶助制度を利用すれば、最低限の葬儀費用を自治体が負担してくれます。
また、故人が住んでいた自治体の社会福祉課や清掃課に相談すると、家財の処分に関するサポートが受けられる場合があります。
例えば、一部の自治体では家財整理の相談窓口を設け、必要に応じて支援団体や専門業者を紹介しています。
遺品の処分に困った場合、福祉事務所や地域包括支援センターに問い合わせることで、利用できる制度を教えてもらえます。
まとめ
遺品整理は、相続人がいるかどうかによって進め方が変わります。
生活保護を受給していた人が亡くなると、相続人が整理を行うのが一般的ですが、相続放棄や保証人がいない場合は、大家や管理会社が対応することもあります。
費用の負担が気になるときは、自治体の制度を活用できるか確認してみるのがおすすめです。
橋本 明
遺品整理士 / 不用品回収・リサイクル業務専門家
個人宅・オフィス・店舗・工場など多様な現場で経験を積み、大型案件にも多数携わる。
2021年に独立し、現在は遺品整理を中心とした事業を運営。
従業員数10名、車両7台を保有し、年間1,000件以上の遺品整理・不用品回収を手掛ける。
埼玉の遺品整理ははしもとサービス
白岡市、さいたま市での遺品整理・生前整理は、経験豊富なはしもとサービスにお任せください。
地域密着で培った信頼と実績をもとに、迅速かつ丁寧なサービスをご提供いたします。
お客様の大切な思い出を尊重し、安心してご依頼いただける対応を心がけております。
是非一度お見積りを。